<参考書籍>
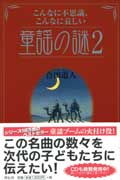
童謡に隠された秘密に迫る、興味深い本です。
童謡の謎シリーズは、2001年〜2003年にかけてのベストセラー。続編も出されました。その中にはCD付きもありますので、興味のある方は調べてみて下さい。著者はもとフォークシンガーで、音楽プロデューサーをされている方です。 当時は、様々な媒体で取り上げられていた記憶があります。
右画像をクリックすると、熱帯雨林にリンクしています。
もっと「ララバイ」参考
| 以下は、代表的な日本の子守歌です。 普段はあまり意識することはありませんが、それぞれの歌には深い由来があります。 |
|
| 江戸子守唄 日本古謡 |
竹田の子守歌 京都地方民謡 |
| ねんねんころりよ おころりよ ぼうやのおもりは どこへいった 里のみやげに なにもろた |
守りもいやがる 盆からさきにゃ 盆がきたとて なにうれしかろ この子よう泣く 守りをばいじる はよも行きたや この在所こえて |
| 五木の子守唄 熊本県民謡 |
中国地方の子守唄 中国地方民謡 作曲:山田耕筰 |
| おどま盆ぎり盆ぎり おどま勧進勧進 おどんが打死だちゅうて おどんが打死ちゅうたば 花はなんの花 |
ねんねこしゃっしゃりませ ねんねこしゃっしゃりませ 宮へ詣ったとき |
| 島原の子守歌 島原地方俗謡 作詞:宮崎康平 |
以下:「島原の子守歌」の歌詞の意味 |
おどみゃ 島原の 帰りにゃ 寄っちょくれんか あん人たちゃ 二つも 山ん中は かん火事げなばい 姉しゃんな 何処行たろかい 沖の不知火 |
歌詞注1):鬼池の久助どんの連れんこらるるばい 言うことを聞かない子は、鬼池の久助さんが連れにくるぞ という意味。鬼池の久助とは女衒(ぜげん)である。女衒とは、人身売買を生業とする者の事。主に
貧しい農村から少女達を買い取って遊郭に売り渡していた。需要に応じ男児を売ることもある。鬼池の久助は実在の人物ではないが、モデルとなった人物はいるらしい。 歌詞注2):あん人たちゃ二つも金の指輪はめとらす あの人達は、二つも金の指輪をはめてるよという意味。貧しい農村ならば本来、金の指輪など持てるはずがない。つまりこの指輪の意味するところは、子供を売った代償である。それを知る村人は「金はどこん金(あの金は、どうして手に入れた金なのか?)」と噂しているのだ。なお財産を金で蓄えるのは、身分が安定しない者達の常套手段である。 歌詞注3):山ん中は かん火事げなばい 山の中が、火事だよという意味。 歌詞注4):青煙突のバッタンフール 青煙突のバッタッンフールとは、香港の船会社バター・フィルのことと言われている。しかしここでは、特定の船会社を指すわけではなく、海外貿易を行う貨物船全般を指す。 歌詞注5):バテレン祭 バテレン祭と言うものが実在するか不明だが、島原地方が隠れキリシタンの里であることはよく知られている。それ故にこの地方の人々は、明治になっても官憲の厳しい監視の下にあり、出入りは長崎のみに制限されていた。このことは島民の慢性的な、窮状を招いていた。 |
| 「ララバイ」 目次に戻る | もっと 「ララバイ」に戻る |